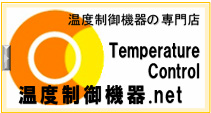トピックス
コラム
2021.10.06
引火点と着火点の違いや注意点を解説
「引火点」という言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。
何気なく「物が燃えるときの温度」と捉えているかもしれませんが、発火点や燃焼点など類似した言葉もあり、厳密な定義はそれぞれ異なります。
そこで本記事では、引火点の具体的な内容や防爆におけるポイントを紹介します。
仕事柄、危険物の取り扱いに関わる方や、防爆に関心のある方は、ぜひ参考にしてください。
引火点とは
まず、引火とは、加熱することで一定の温度まで上がった可燃性物質が、火を近づけた時に燃焼し出す現象を指します。
引火点とは、可燃性物質が燃焼するときの最低温度のことです。
厳密には、可燃性物質は温度が上がることで、可燃性の蒸気を発散します。
この可燃性蒸気と空気が混合したときの濃度により、引火の有無が決まります。
つまり、可燃性蒸気の濃度が高く、蒸気燃焼可能な爆発範囲(燃焼範囲)に入った時に、引火するのです。
アルコールランプは、液体の蒸発燃焼を利用した一例で、芯を上がって蒸発したアルコールに火を近づけることで引火します。
発火点との違い
引火点と比較説明されるのが、発火点です。
発火点とは、着火源がなくても、何らかの影響で高温となった可燃性物質が燃える最低温度を指します。
一般的に、発火点は引火点よりも高いです。
灯油やガソリンの発火点は約260度で、この温度を上回ると着火源がなくても、自ら燃え始めます。
常温の空気中でも自然に発熱し、熱を蓄積することで発火点に達し、燃焼し始める「自然発火」という現象も起こり得ます。
自然発火の原因は酸化熱や吸収熱、分解熱などがありますが、日常生活にも危険が潜むため要注意です。
実際に、アロマオイルが付着したタオルが自然発火し、火災を起こしたエステ店もあります。
燃焼点との違い
あまり馴染みのない燃焼点ですが、危険物を取り扱う上では、知っておいて損はありません。
燃焼点とは、引火した可燃性物質が燃焼を5秒間維持するための最低温度のことです。
引火点と発火点の間の温度と考えれば良いでしょう。
引火後に、可燃性物質自体の温度が燃焼点を下回れば、燃焼は止まります。
反対に、引火後も可燃性物質自体の温度が燃焼点を上回れば、燃焼し続けます。
引火点の例
代表的な可燃性物質の引火点は以下の通りです。
可燃性物質の引火点
- ガソリン -43度以下
- シンナー類 -9度
- メチルアルコール 11度
- 灯油 40~60度
- 軽油 40~70度
- 重油 60~100度
- 機械油 106~270度
- ごま油 289~304度
- 菜種油 313~320度
ガソリンは-43度以下と極めて低く、引火しやすいです。
ガソリンによる火災・爆発を防ぐためには、ガソリン容器から蒸気が流出しないようしっかり防ぎ、火の気がある場所や直射日光の当たる場所を避けて取り扱い・保管しましょう。
防爆における引火点
火災による爆発を防ぐためには、可燃性物質が引火しないよう、電気設備に防爆構造を施さなくてはなりません。
危険物の規制に関する政令により、防爆構造の設置義務は以下の条件に当てはまる事業所や工場に課されます。
電気設備を防爆構造としなければならない範囲
- ①引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場合
- ②引火点が40度以上の危険物であっても、その可燃性液体の引火点以上の状態で貯蔵し、または取り扱う場合
- ③可燃性微粉が著しく浮遊するおそれのある場合
危険物を取り扱う際は、引火点を含む、物質の特徴をしっかり把握しましょう。
防爆するためには引火点に要注意!
いかがでしたでしょうか。
今回は、引火点の定義や防爆における重要性を紹介しました。
危険物を少しでも取り扱う場合は、防爆構造の設置を推奨します。
防爆工事でお悩みの方は防爆工事.comへご相談ください。