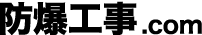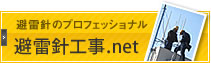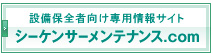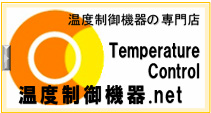工事現場や事業所などで働いている方にとって最も怖いのが爆破事故ではないでしょうか。
日々働いている中での安全管理は雇用者の義務であり、安全が保証された環境で働くことは従業員の権利でもあります。
そういった観点から、労働環境における電気機器には、防爆構造が導入されたものを使用しなければならないことが法律によって定められています。
本記事ではその防爆構造の1つ、「非点火防爆構造」について解説しています。
強固な防爆対策を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
「非点火防爆構造」とは
「非点火防爆構造」、(別名:「n型防爆構造」)は、しばしば「nA」という記号で表され、
①機器の状態に関わらず、発火源となる可能性が低い
②機器の近くの爆発性ガスなどに引火する危険性が低い
上記の2点を満たしている電気機器に導入されます。
「簡易防爆」とも呼ばれ、保護水準を引き下げることにより、構造上の条件や導入要件の緩和がなされています。
そのため、主に、LED照明器具や簡易設計の電気機器などに用いられるケースが多いです。
「非点火防爆構造」が適用される危険箇所の分類
危険箇所は「0種」、「1種」、「2種」、「非危険箇所」の4つに分類されます。
・0種→現場の環境に関わらず、爆発性のガスや可燃性物質が長時間存在する可能性がある箇所
・1種→通常状態において、爆発性のガスや可燃性物質が発生する危険性のある箇所
・2種→通常状態で爆発性のガスや可燃性物質の発生率が低く、発生したとしても短時間しか存在しない箇所
・非危険場所→電気機器の使用に際して特別な措置を取らなくてもいいと判断された箇所
爆発性ガスや電気機器を扱う工場や事業所は、上記の0種から2種のいずれかに該当します。
「非点火防爆構造」が導入された機器は、「2種」でのみ使用が認められており、0種や1種に該当する危険箇所では使用することができません。
防爆の保護水準を下げているため、機器内部への導入は容易である一方、危険度の高い場所には導入が認められていないのが現状です。
ですが、日本国内の防爆エリアの80%が「2種」に該当すると言われています。
そのため、軽工業などの「2種」に該当する工場にとっては、適切な箇所に導入さえしていれば安全性も担保された上でコストも抑えられるため、まさに一石二鳥の構造と言えます。
電気機器の定期的なメンテナンスを
以上、本記事では防爆構造の1つ「非点火防爆構造」について解説しました。
防爆対策を検討する上での参考になりましたでしょうか。
防爆構造を導入しているから大丈夫と安心するのではなく、内部の腐食やネジの緩みがないかなど、安全のために電気機器の定期的なメンテナンスは行っていくようにしましょう。
防爆工事でお悩みの方は防爆工事.comへご相談ください。
(https://boubaku.seikun.co.jp/)